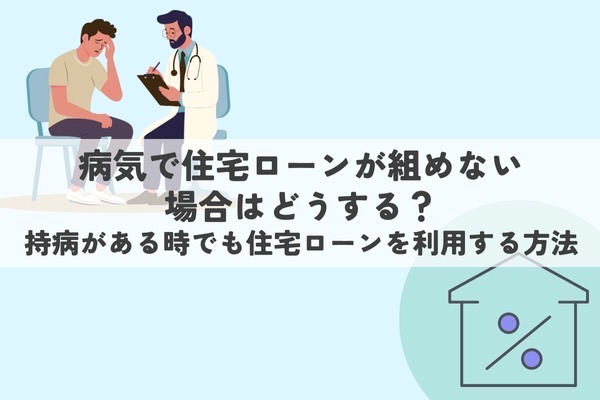
病気でも住宅ローンを利用できる?持病がある方の対応方法
住宅ローンを契約するとき、多くの金融機関では「団体信用生命保険(団信)」への加入を求めます。
契約者が保険に加入できる健康状態であることも、住宅ローンを利用するための条件の一つなのです。
契約者が保険に加入できる健康状態であることも、住宅ローンを利用するための条件の一つなのです。
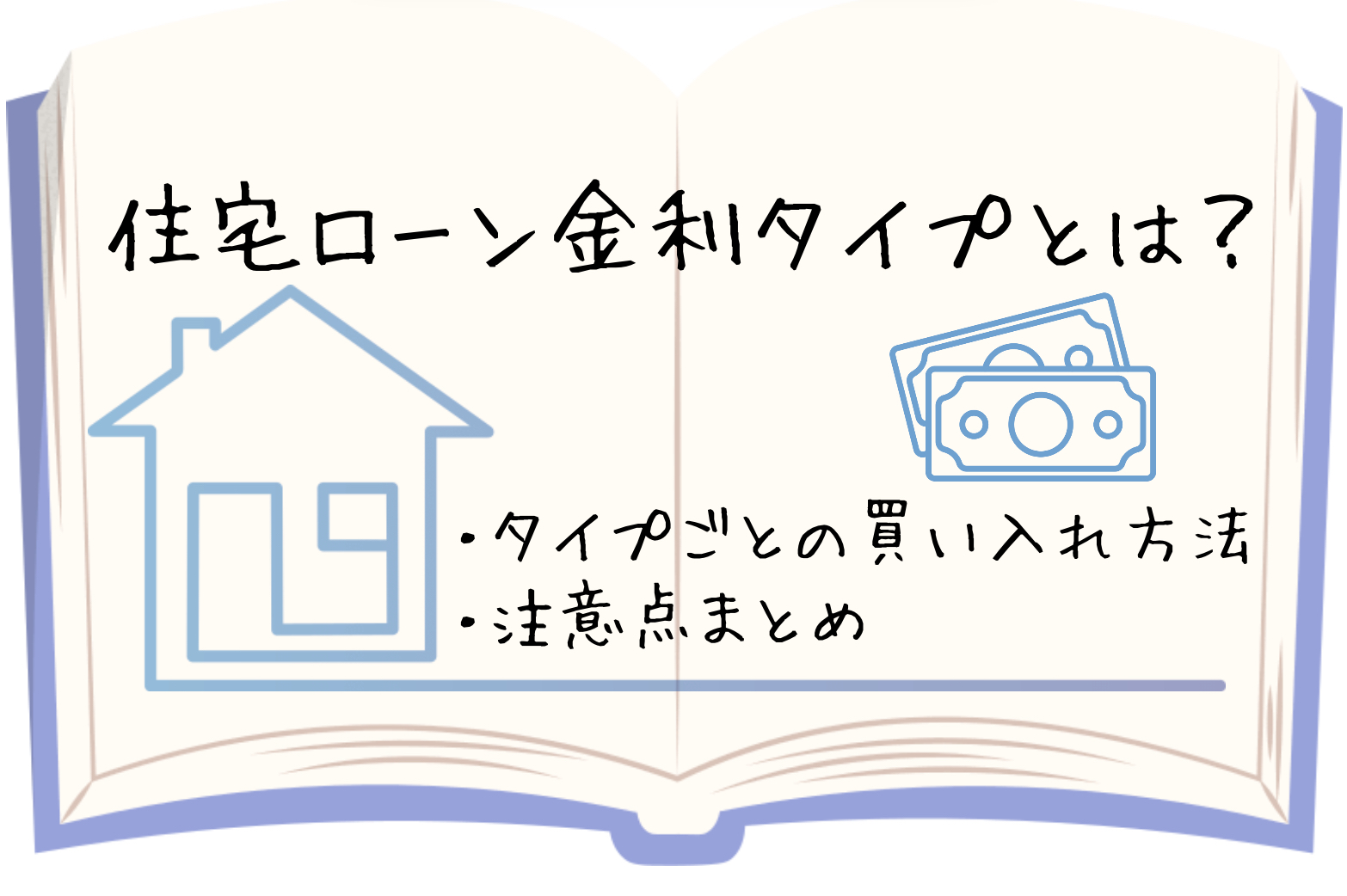
住宅ローン金利タイプとは?タイプごとの借り入れ方法・注意点まとめ
住宅を購入する人の多くは、住宅ローンを利用して資金を用意します。
その場合、どの金利タイプを選ぶかによって返済の負担が大きく変わってきます。
その場合、どの金利タイプを選ぶかによって返済の負担が大きく変わってきます。